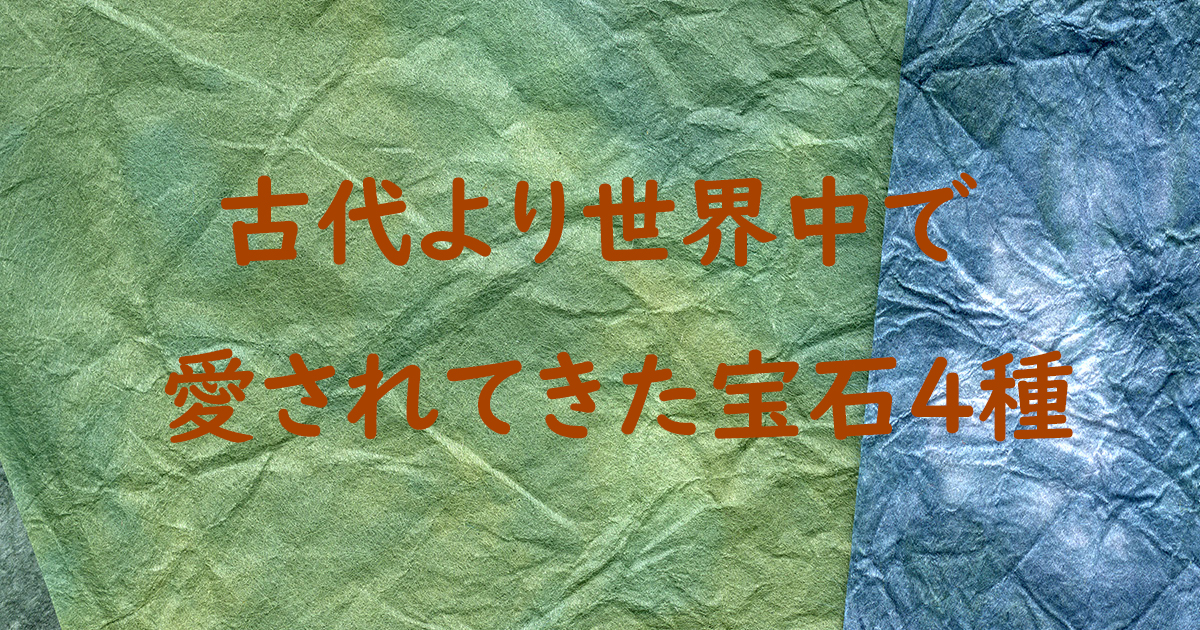古代の人々が実際に使っていた石は、博物館でわずかに見られるだけですが、
宝石そのものは今でも存在しています。
古代から愛されてきた宝石って、何か特別なロマンを感じますね。
日本でも、勾玉などは、ヒスイ、メノウ、水晶を材料に作っていました。
ヒスイといえば、新潟県の糸魚川が有名で、下流域や河口などでは、
規制がもちろんありますが、今でも拾えたりするそうです。
今回取り上げる宝石は、紀元前数千年前から人々にとって、
最上のパワーストーンであり、薬でもあり、美の象徴でもあった宝石たちです。
もくじ
古代から愛されてきた石とは
早速ですが、古くから人々が愛してやまなかった宝石とは、
ラピスラズリ
オパール
ターコイズ
エメラルド
ラピスラズリは、紺碧の海、エーゲ海のような目の覚めるような青が印象的な、
染料や薬にも用いられていたカッターにやさしい加工しやすい宝石です。
オパールは、ラテン語の「貴石」を由来に持つ、
特に古代ローマ人に重宝された宝石です。
トルコ石/ターコイズは、メソポタミア文明をはじめとして、
アメリカ先住民の間で5000年にもわたって採掘されてきた宝石です。
最後のエメラルドは、インカ帝国をはじめ、古代の歴代の王たちが、
栄華の象徴や繁栄の源として身に着けたり飲んだりもした
パワーストーンの起源のような宝石です。
それでは、モーゼやクレオパトラなど、著名人が愛していたことでも有名な宝石をはじめ、
儀式や祭祀でも重要な役割を果たしてきた4つの宝石について取り上げていきたいと思います。
ラピスラズリ
ラピス・ラズリとは、ラズライトをはじめ、カルサイトやダイオプサイドなど
様々な方ソーダ石グループが集まった宝石です。
もともとアラビア語やラテン語で、見たままの「青い石」を意味しています。
しかし、この「青」は侮れなくて、この青の色合いにより
価格差が30倍もついてしまう格差の激しい宝石なのです。
古代エジプトでは、ラピスラズリは大きな役割をはたしていました。
宝飾の材料となる宝石は多種多様で、ナイル川上流域のヌビアの金をはじめ、
紅海近くの鉱山(クレオパトラの鉱山)のエメラルド、遠方の各地から琥珀やトルコ石などです。
その中でも、ラピスラズリは、なんと遠くはアフガニスタン
(恐らくは、北東部の鉱山から)から、取り寄せていました。
アフガニスタンは、かなり昔から宝石採掘の拠点だったようです。
また、ラピスラズリは宝飾以外でも使われていて、粉状にして顔料をはじめ、
薬や化粧品としても価値がありました。
最初のアイシャドウに使われたと言われてます。
またラピス・ラズリは、古代エジプトでは、宝石が身を飾るのはもちろんのことですが、
病を治す力や神秘のパワーなど普遍的な秩序を維持し、不滅の生命を与える力がありました。
このあたりは、現代のパワーストーンにも通じるところがありますね。

ラピスラズリで作られたプタハ(出典:メトロポリタン美術館CC0)
現代では、ラピスラズリは比較的流通量が多く、
身近な宝石過ぎてピンとこない方々いらっしゃることでしょう。
しかし、手に取ってみると、この鮮やかな「青」はとても綺麗で、
古代から魅了されてきたのもうなずけます。
ラピスラズリの青味は、主にラズライトに起因するものですが、
純粋なラズライトの方が商品価値が高く、より高値で取引されています。
しかし、きらきらとした金粉のような黄鉄鉱が散りばめられたラピス・ラズリも、
高級感があり、魅力にあふれています。
オパール
オパールのあのきらきらといろんな色がきらめく遊色効果は、
古代の人々に驚きと賞賛とを持たらしました。
そこには、超自然的な何らかの効果と力があるのではないかと信じられてきたのです。
アラビアでは天から雷とともにある石として、
ギリシャでは病魔退散のお守りとして用いられていました。

エチオピア産オパールの原石
オパールの産地としてはオーストラリアとエチオピアが有名ですが、
オーストラリアの原住民アボロジニにも、オパールと神にまつわる伝説が残っています。
このように、岩石を割れば、様々な色をまるで万華鏡のように、
キラキラとさせる不思議な石は、人々に大きな驚きをもたらし、
未知のパワーを持っていると思われてきたのです。
トルコ石/ターコイズ
トルコ石/ターコイズと言えば、12月の誕生石として現在でも有名で、
どこか私たちには、インディアンの装飾品というイメージがあるのですが、
実はヨーロッパや南米の古代遺跡から発見されていて、古くから愛用されてきた宝石です。
また、13世紀までは、トルコ石という名前ではなくて、
美しい石を意味する「カレース」と呼ばれていました。
カレースという名も何だか優雅で、この名でもよさそうです。
約6000年前では、現在のイランであるペルシャがトルコ石/ターコイズの主要産地でした。
十字軍とともにヨーロッパにもたらされたのが、この名前「トルコ石」のそもそもの始まりでしが、
このトルコ石の名前の由来が少し複雑で、ヨーロッパにもたらされた頃は、
トルコ人による王朝が、トルコ石の古い鉱床を所有していて、
このトルコ人がもたらしたということで、「トルコ石」と呼ばれるようになったのです。
1800年頃のマリー・ルイーズ皇后の王冠が、エメラルドだったのが、
すべてトルコ石に替えられたのは有名なお話で、
当時のトルコ石の価値が高かったことがわかります。

トルコ石のマリー・ルイーズのティアラ
(スミソニアン美術館より)
エメラルド
古代の富裕層が欲したキーワードといえば、ラピスラズリに代表される「青い石」と
もう一つまぶしいほどの輝きを放つ「黄金」ですが、
この緑鮮やかなエメラルドも紀元前1300年頃には、すでに採掘されていたと言われています。
エメラルドはそのグリーンの色合いが人々を魅了し、深く社会と関わっています。
アイルランドはエメラルドアイルですし、ワシントン州のシアトルはエメラルドの都です。
タイで最も神聖な宗教的象徴は、翡翠を彫られているにもかかわらず、
エメラルド仏と呼ばれています。
古代の装飾、特に古代エジプトや古代ローマ時代の装飾品に、多く見られることも、知られています。
これらのほとんどは、現在では枯渇してしまいましたが、
ジャーバルスカイットとジャーバルザブグラーという
通称クレオパトラ鉱山と呼ばれるところから産出されました。
古代エジプトでは、このグリーンカラーが繁殖と命の印であり、
ヨーロッパではてんかんの発作を抑えるため身に着けていました。

エメラルド原石を使った彫刻 CC By- SA2.5でライセンス供与されています。
エメラルドは、神からソロモン王に与えられた4つの宝石の1つであった、
という伝説が残されています。
ちなみに、4つの石の他の3つはルビー・ラピスラズリ・トパーズです。
これらの4つの石は、すべての創造物に対する力を王に与えたと言われています。
硬度は8にもかかわらず、多くの内包物のために脆いところも魅力の一つです。
エメラルドの産出は広い範囲にわたっていて、
産地によって、色合いに特徴がある珍しい特性もあります。
エメラルドの取り扱いを長くしていると、その色味だけで産地が分かってくるようです。
それは、結晶が生成していく過程で、取り込む物質にそれぞれの産地の特性が現れるためです。
例えば、ジンバブエのサンダワナ鉱山は、1900年代の後半に見つかった
新しい鉱山ですが、小粒で、少し黄色味が入った美しい色合いをしています。
また、同じ緑でもザンビア産の濃い緑はバナジウムに起因し、
コロンビア産はクロムによる緑の色合いとは異なる特徴を持っています。
最後に
古代から愛されてきた宝石は、今でも人々を魅了し続けています。
ラピス・ラズリやトルコ石/ターコイズは、ビーズをはじめとした宝飾材料に人気の高い宝石の一つですし、
エメラルドという言葉は、宝石ばかりでなく、色味の表現をはじめ深く人々の生活に溶け込んでいます。
また、オパール、特にブラックオパールの響きは高級な宝石の代名詞の一つになり、
近年、枯渇する良質なブラックオパールの鉱床が増える中、その価値はうなぎのぼりとなっています。
皆さんも、この古代から愛され続けている4大宝石を、ひとつ身に着けてはいかがでしょうか。
身近に持てば、その価値を実感することと思います。